キルト専門の編集者 市川直美さんのおすすめ『WHO’D A THOUGHT IT』
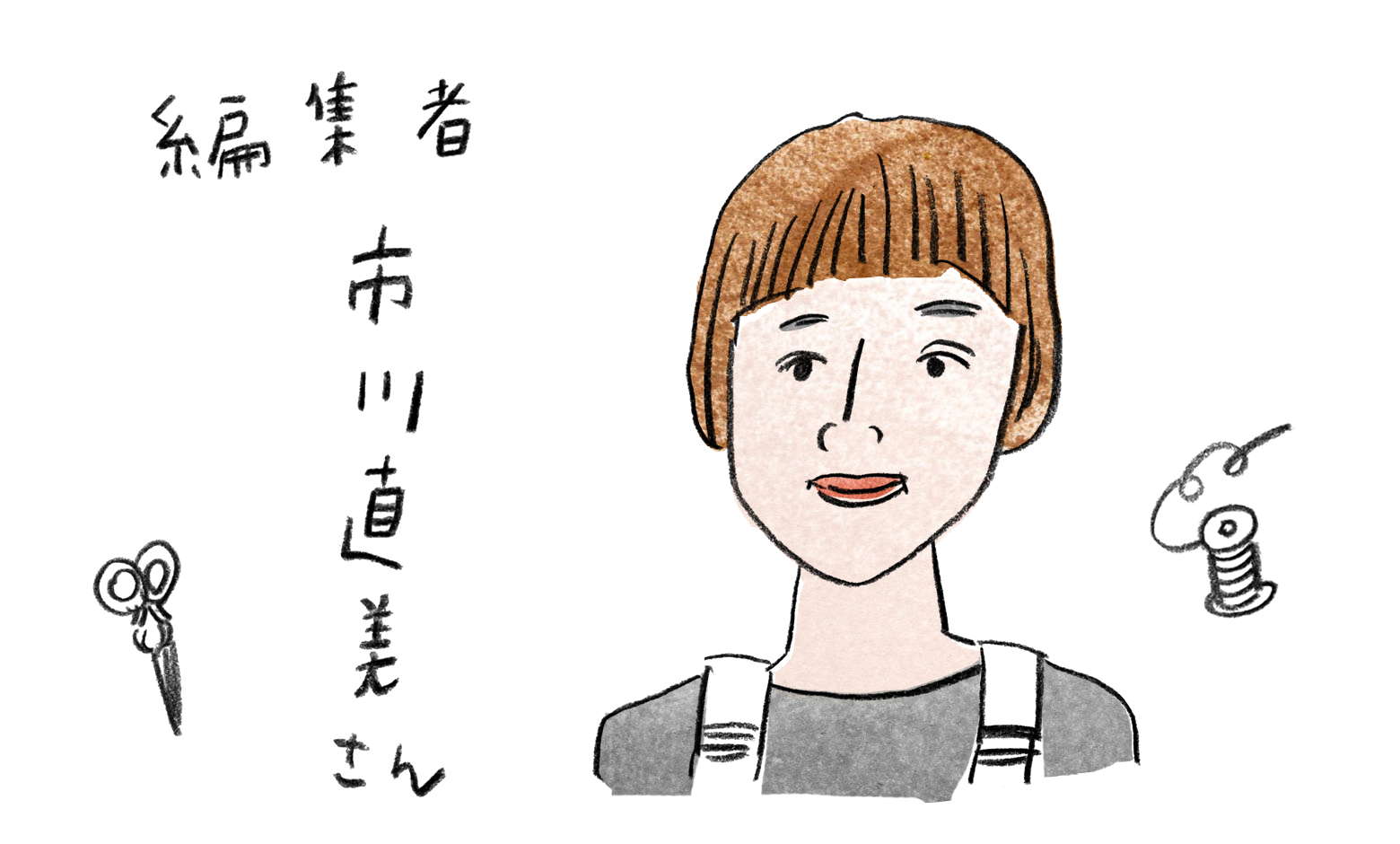
キルトとの関わりは長くこれまでキルト雑誌3冊の編集長を務めました。キルトの仕事の中で一番夢中になったのは海外取材で、訪問国は30カ国を超えています。取材を重ね分かったことは「布をつないで何かを作る」習慣や文化は地球上の人々の日々の暮らしの中で大切に育まれてきたということ。そこにあるのは国も人種も超えた誰もが共有できるささやかな楽しみです。行く先々での発見を拾い上げ、つながっている糸を手繰り寄せ解いて引っ張るうちに、繋がることや気づいたことにハッとして…。キルトを巡る旅はキリがなく、私の旅はまだまだ途中なんです。
Q
市川さんのおすすめの本について聞かせてください。
『WHO’D A THOUGHT IT ーImprovisation in African-American Quiltmakingー』(Eli Leon/San Francisco Craft & Folk Museum/1985年)
アフリカ系アメリカ人の作るキルトを集めた本。アメリカのサンフランシスコのクラフト&フォーク美術館刊。美術館での展示に合わせて発行されました。当時(1985年)アフリカ系アメリカ人のキルトがクローズアップされることはほぼなかったことや、収録されたキルトの自由奔放な色彩やデザインに多くの人が驚き大きな話題になりました。そこにはそれまでお馴染みだった所謂、幾何学模様のパッチワークのパターンが歪み崩され、まるで即興のジャズに通じるデザインが展開されていたのですから。

Q
この本のどんなところが心に残ったのでしょうか。
この本で初めてアフリカ系アメリカ人のキルトを知ることになりましたが、ショックに近い衝撃を受けました。作者は単に家にある残り布を形なりにただ縫いつけているのですが、仕上がったキルトはまるで緻密に計算されたモダンアートのように見えているのです。作者の意図せずにアートに仕上がっていることの不思議と偶然。短絡的ですが彼らが生まれながらに携えているであろう卓越したリズム感をそこに感じてしまいまた感激…。書名の和訳は「これを考えたのは誰?」。まさに同感。キルトは形も色も自由に操って変化させ、最後に辻褄を合わせれば良い。「そうでなければならない」固定概念が取り払われ、私自身の捉え方の枠を外すことができた記念すべき本です。
Q
現在のお仕事・ご活動、ものづくりにはどう繋がっていますか。
いろんな人種のキルトを知りたいと思うきっかけになったのがこの本。地球上にいろんなキルト(布つなぎ)があるはずで、アメリカだけでなく世界中で実物を見たい触りたいと、夢見るようになりました。その後、世界の旅を実現させるためあらゆる手段を考えて知恵を絞り、粛々と着々と夢をかなえていきました。アフリカ系アメリカ人のキルトについては、その後多くの出合いを重ね、アメリカのセンセーショナルな歴史ストーリーにも触れていくことになります。

Q
最後に、手芸・手仕事・ものづくりの魅力はなんだと思いますか。
手芸本の編集や企画の仕事をしておりますが、私自身は作りません。しかし取材の時に各地で買い求めたり現地の方にいただい布や作品をたくさん持っております。それらは私の旅の記憶を思い起こさせてくれる小さなピース。時々出して眺めては思い出を手繰り、また大切に仕舞って、を繰り返す大切な宝物。手仕事は人々の側にあって喜び、悲しみの時を共有するもの。豊かな時間を運んでくれるものです。そして作り手の想いを未来に運ぶ大役も密やかに担っていると気づきハッとすることもよくあります。

PROFILE
市川直美 Naomi Ichikawa
学生時代にアメリカ文化の一つとしてキルトに興味を持つ。大学卒業後、編集の仕事に就きキルト専門の編集者となる。これまで「パッチワーク通信」「よみうりキルト時間」「キルトダイアリー」の編集長を務めた。編集以外では、国内外のフェスティバルや美術館でのキルト展示の企画や、キルトツアーの企画にも携わってきた。現在は、2025年アメリカで出版予定の日本のキルトを紹介する本を準備中。著書に「プリンスエドワード島 キルトの旅」「英国キルト紀行」「アメリカキルト紀行」など。
