第11回 家族に受け継がれるスイスの木彫り人形-姉妹が行く! 世界てくてく手仕事の旅
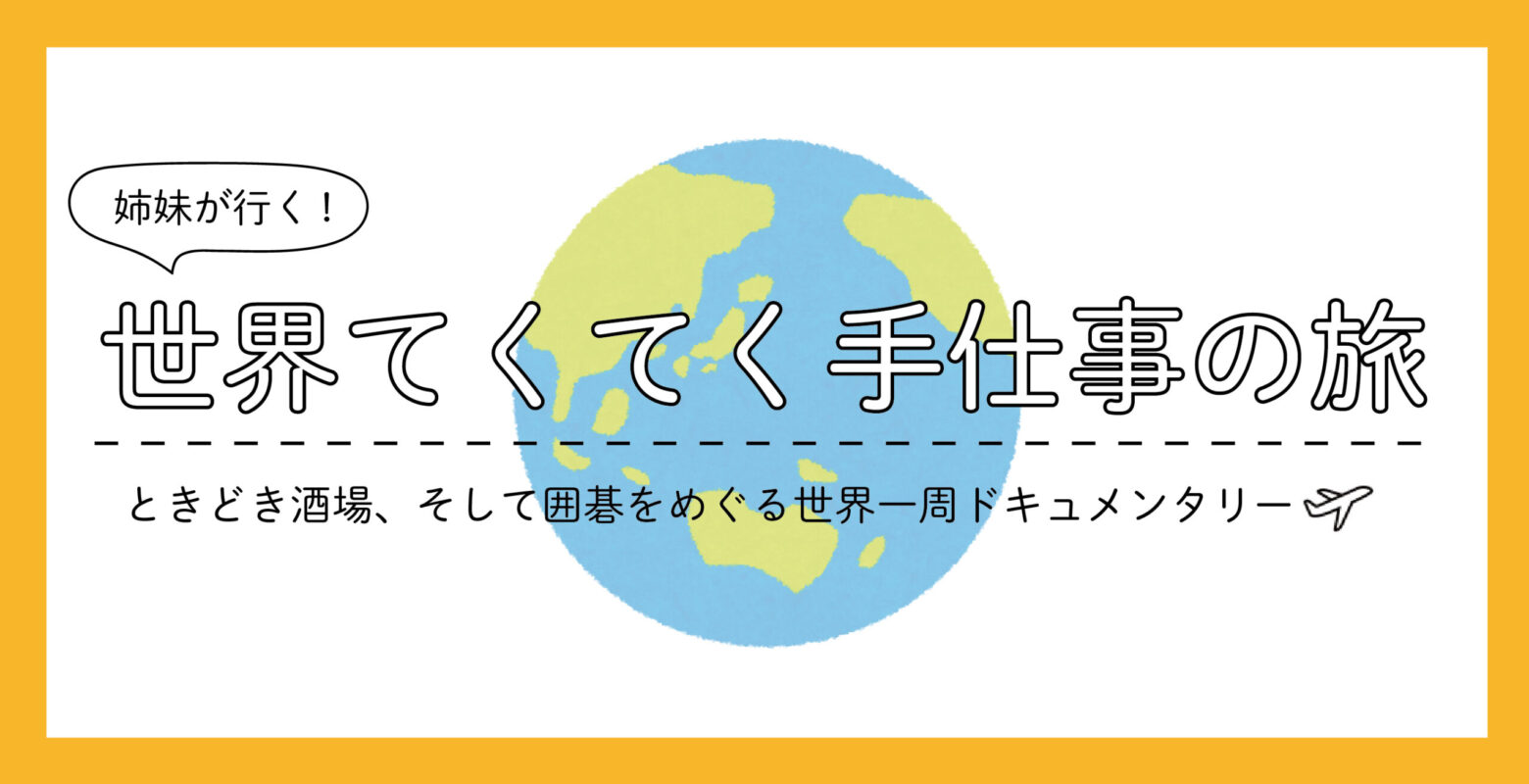
山岳文化のスイス
連載11回目はスイスの木彫りについて。スイスはヨーロッパの真ん中あたりに位置する、アルプス山脈に囲まれた自然豊かな国です。『アルプスの少女ハイジ』の世界観を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?
今回のスイス旅は国内最大の都市・チューリッヒを中心に4日間滞在しました。日帰りで木彫りの街・ブリエンツ、山岳鉄道が走るリギ山にも足を運びました。また一度スイスを出て、後日クリスマスの時期に訪ねた際にはチューリッヒのクリスマスマーケットも楽しみました。


スイスの地形は山脈に囲まれており、農業に適した土地が少なく、大規模な工業化も難しいため、地域ごとに職人技を活かした小規模な手工業が発展しました。また、永生中立国として政治が安定しており、文化や芸術、技術的なものが発展しやすかったため、オルゴールや時計、刺繍や切り絵、木工や彫刻、ナイフなど、高品質で長持ちする職人技の手仕事も多いです。日本の丁寧なものづくりにも通じるものがあるように感じます。今回はその中から、スイスの木彫り人形についてご紹介します。







木彫り人形との出会い
スイスの木彫り人形に興味を持ったきっかけは、チューリッヒにあるSchweizer Heimatwerkというスイスの手仕事を扱うお店を訪ねた時のこと。店内に並んだ木彫りの人形のなんともいえない温かみと、キリスト降誕の馬小屋の世界観に一目惚れをしました。





Schweizer Heimatwerkのオーナーのニコラスさんがとても親切にいろいろ教えてくださり、「この木彫り人形は一つひとつ職人さんの手作りで、手頃な値段ではないけれど、スイスでは毎年クリスマスや誕生日といった特別な日に一つずつ大切に集めている人もいるんだよ」と話してくれました。その話を聞くうちにもっと知りたいと思うようになり、工房の場所と名前を教えていただき、実際に訪ねてみることにしました。


木彫りとブリエンツの歴史
木彫りや木工で有名なブリエンツという街はスイス中部のブリエンツ湖の東側に位置し、近くの森林で良質な木材が育ちます。18世紀後半、スイスは農業中心の社会でしたがアルプス周辺は土地が狭く厳しい気候条件で農業だけでは生計を立てるのが難しかったため、冬の農作業のできない時期の農民の副業として木彫りが発展していきました。


19世紀後半にはイギリスの富裕層を中心にアルプスの観光ブームが起こり、スイスの伝統衣装を着た木彫り人形や、アルプスののどかな動物や農作業の風景、聖書のシーンの一部を再現した人形などが土産品として人気になり、木彫り産業が発展していきました。
また、高級家具や高級置き時計に施される木彫り細工も富裕層に人気があったため、ブリエンツの木彫りは高い付加価値を感じさせる技術が向上。それにより、木彫り人形の動物の毛並みも細部まで再現されるような精巧な美しさが発展しました。加えて木の質感を活かした優しいペイント、スイスの素朴な日常の雰囲気を合わせ持つのが特徴的です。


1862年にはスイス政府の支援もありSchule für Holzbildhauerei(シューレ・フュア・ホルツビルトハウアライ、日本語訳でブリエンツ木彫り学校)というスイスで唯一の木彫りの専門学校が設立され、ブリエンツはスイスの木彫りの中心になりました。
20世紀の世界恐慌や第二次世界大戦による観光業の衰退と安価な工業製品の普及によって、スイスの伝統的な木彫り産業は衰退していきますが、伝統工芸を保存する動きがあり、観光業の復興とともに再評価されています。




木彫り人形の工房を訪ねて
ブリエンツの小さな街には、木彫りのオブジェやさまざまな木彫りの工房やギャラリーが並びます。




Schweizer Heimatwerkのオーナーのニコラスさんに教えてもらった木彫り人形を作っているHuggler Holzbildhauerei AGという工房を訪ねました。ブリエンツの案内所にもどこの工房を見たらいいか伺うと、「Huggler Holzbildhauerei AGはブリエンツの中でも特に重要な工房だよ」と教えてもらいました。

Huggler Holzbildhauerei AGは現在のオーナーのビートさんで 5代目になるといい、1900年ごろから約100年以上続いています。1915年には創設者によってデザインされた、”オリジナル•スイスのキリスト降誕”と呼ばれるシリーズであるキリスト降誕の場面の木彫り人形が誕生し、現在も同じデザインで製作されています。 100年以上にわたり、伝統的な技術とデザインを受け継いでいるため、買い手は親から子へと世代を超えてコレクションし、毎年少しずつコレクションを増やす喜びを味わえます。

この工房には8人の職人さんがおり、少数精鋭の安定したメンバーで少しずつ技術を高め、ゆっくり職人さんを育てているそう。


この工房の木彫り人形は日用品や必需品ではなくラグジュアリーなものだからこそ、一つひとつ丁寧に時間をかけて作り上げられ、伝統的で高い技術を継承することができます。手仕事の技術を紡いでいく上でこういったトップレベルの工房の役割というのは大きいと実感します。

スタッフさんが、「約80年前、貧しい農民が観光客向けに売ったのが始まりだけど、今ではスイスの地元の人がここの木彫りの人形を誕生日やクリスマスの時に、毎年一つずつ大切に集めてくれて、約100体ほど持っている家族もいるのよ。わたしたちの工房の木彫り人形を親から子どもへと家族に受け継ぐ文化が生まれていて、そのコレクションを家族に伝わる人生の宝物のように思ってくれていることをうれしく思う」と話してくれました。



もともと観光客向けに始まった手仕事がこういった形で地元の人にとって新たな文化として続いているのが興味深く、手仕事にはいろいろなルーツがあると実感しました。
また、スイスは今でこそ世界で最も豊かな国の一つだけれども、当時貧しかった農民の生活や社会情勢を知れるのも、手仕事の背景を深く知る面白さに思えます。


手仕事から知る当時の暮らし
実は、チューリッヒにあるスイス国立博物館を訪ねた時のこと。スイスの手仕事の歴史が展示されている場所にブロックプリントがありました。19世紀に世界中で流行しインドやネパールでも見たブロックプリントをスイスでも見かけた時、手仕事が世界中で繋がり、時代や文化を象徴するものの一つであると実感しました。
同じブロックプリントでもスイスは小さい国だったために大規模な工場が発展せず、小さな工房で職人の技が継承された細かく美しいデザインが主流で、地域性があるのも面白いです。


木彫り人形ができるまで
Huggler Holzbildhauerei AGで実際に職人さんが木彫り人形を作る様子や工程を教えていただきました。木彫り人形は基本的にはライムの木で作られています。ライムの木は木目が細かく均一で柔らかいため彫刻がしやすく、軽量で扱いやすく時間が経っても変形しにくいという特徴があり、ブリエンツやスイスで簡単に手に入るため、木彫り人形にはぴったりです。

1番左から3番目までは、古い機械を使いながら職人さんが切り出していくそう。3番から4番目は彫刻刀を使い全て手作業です。1番左から2番目とざっくり切り出す職人さん、2番目から3番目と形を作る職人さん、3番目から4とディテールを彫刻していく職人さん、最後にペイントをする職人さん、と専門的に分かれているそう。

実際に彫刻していく様子を見させていただき、モデルを見ながら何十本もの彫刻刀を使い分けて彫っていく様子はまさに職人技です。一つひとつ彫刻が進むごとに命が吹き込まれるようで、木に温もりが宿っていきます。

また、お客さんにオーダーされた時やクリスマスで新しいデザインがほしい時、また新しい動物を作ろうと思った時などに新しいデザインを考えるといいます。
職人さんの想い
こちらで働く女性の職人さんにもお話を伺いました。シルビアさんは4年間ブリエンツ木工学校で木彫りを学んだ後、こちらで4年ほど木彫り職人として働いています。自分の手で何かを作れて、クリエイティブな仕事がしたかったそう。

木彫りの人形を作るのは初めは難しいですが、50体ほど作ったあとにこの形はどうやったら切り出せるか、この形にはどの彫刻刀が合うか、だんだんと分かるようになったと言います。

現在は1つの人形を2時間ほどで作り上げ、1日4体ほど制作するそう。大きい人形は作る機会が少なく経験を積める回数も少ないため、最初の削り出す工程が難しいと言います。
職人さんの得意不得意によって、動物をメインで制作する職人さん、人をメインで制作する職人さんと別々のスペシャリストになっていくそう。



もう1人、ブリエンツ木工学校に通う17歳の若い職人さんにもお話を伺いました。
彼女もまた、木彫りはクリエイティブで楽しそうというきっかけから、木彫り職人になりたいと思ったそう。初めは板から練習して、彼女が彫ったものをシルビアさんに見せてアドバイスをもらっていました。ブリエンツ木彫り学校ではデザインや木彫りの技術、3Dモデルの制作などを学んでいるといいます。

長い時間をかけて大切にされるもの
旅先で出会ったスイス人の友人は「両親が子どもの頃遊んでいた、牛の形をした木のおもちゃをおばあちゃんは捨てずに大切にとってあると思う」と話してくれました。量産品を消費してすぐに捨てて新しいものを購入する、という現代に多いライフスタイルとは違った、いいものを長く大切に使うというスイスの日常を教えてもらいました。
また、Huggler Holzbildhauerei AGの木彫り人形のように、日常生活で使われる何気ないものとはまた違った、毎年一つずつ特別な想いを込めて購入し、家族の、そして人生の宝物に何年もかけてなっていく手仕事の品というのもとても素敵なものに思えました。


Huggler Holzbildhauerei AGを訪ねた後日、Schweizer Heimatwerkのオーナーのニコラスさんにお礼のご連絡と、ニコラスさんのご家族も集めているかお話を伺うと、とても素敵なお話をしてくれました。
「自分の家の木彫り人形のコレクションは、曽祖父が初めの一体の人形を買ったのが始まりで、そこから毎年クリスマスに一体ずつ集めてキリスト降誕の馬小屋が少しずつ完成していったんだ。そして祖父母、両親へと引き継がれ、マリアとイエスとヨセフだけだった馬小屋は、毎年新しい動物や羊飼いが加わり、大きなコレクションになっていったんだよ。スイス産の最高級の乾燥させたライムの木と、自然の色を使った丁寧な彩色という高品質の技術を守るこの工房の手仕事のおかげで、人形の個性や外観は今もしっかりと保たれているままで、だからこそ私たちは将来の世代にもこの人形とその伝統を受け継いでいくことができるんだよ」と教えてくれました。

もともとは観光客向けに始まった手仕事が、形を変えて地元の人に愛され、手仕事が衰退して量産品や消耗品が溢れる現代で、こうして丁寧に作られたものが家族の何代にも渡って紡がれる文化として繋がっていく様子が美しく、心に残った手仕事の一つになりました。

shimaitabi の食コラム ~スイス編~
2024年12月21日 @チューリッヒHuggler Holzbildhauerei

スイスのご飯と聞いて、大きな半円状のチーズの表面をとろーりと溶かし野菜やベーコンにかける”ラクレット”を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか?
私もスイスを旅したらラクレットを食べてみたい!と夢見ていました。友人のご実家にホームステイさせていただいた時、「それなら、明日の夜ご飯は家でラクレットにしよう」と言われて歓喜。ラクレットはてっきりレストランで食べるご飯なのかと思っていたら、日本でいう”たこ焼き”のように家庭の定番料理で、一家に一台、ラクレットメーカーとチーズフォンデュのセットがある家庭が多いそう。スーパーにはラクレット用に長方形にカットされた専用のチーズが売っています。
ラクレットメーカーは人数分ある四角い小さなフライパンの上でカットされたチーズを溶かし、ゆでたじゃがいもにかけて食べます。付け合わせはピクルスやドライトマトが定番。準備も簡単で人が集まった時に、みんなで食卓を囲みゆっくり食事を楽しめるので、夏はラクレット、冬はチーズフォンデュがスイスの日常なんだとか。
チーズと一緒に温めた洋梨が甘塩っぱく、付け合わせのピクルスもさっぱりとさせてくれてとっても美味しく、手軽さも相まって、帰国したらラクレットメーカーを家に一台ほしいと思ったのでした。
次回もお楽しみに!
PROFILE

世界一周 姉妹旅 毛塚美希・瑛子 Miki, Akiko Kezuka
その土地の暮らしと文化に触れるのが好きで、世界一周の旅に出た20代の姉妹。手仕事を中心にライティング、買い付けを行う。姉は元インテリアメーカー勤務、妹は元食品メーカー勤務。手仕事、食と酒場、囲碁をテーマに、自由きままに各地を巡る。
小さな村でホームステイ、工房巡りに、そのまま地元の人達と乾杯! そんな日々の暮らしに溶け込むその土地らしさを感じたままの温度でお届けします。
HP: https://sites.google.com/view/shimaitabi?usp=sharing
